出生から上杉家景勝に仕えるまで
出生に関して信憑性のある資料はなく、永禄3年(1560年)樋口兼豊(ひぐちかねとよ)の長男として生まれ、幼名は与六(よろく)。母は藤(もしくは蘭子)と言われている。
永禄7年(1564年)、上田長尾家当主で坂戸城主の長尾政景(ながおまさかげ)が死去。当時9歳だった長尾政景の子で長尾顕景(ながおあきかげ:のちの上杉景勝)は、上杉謙信の養子になる。この時、直江兼続は上杉景勝の近侍となったと言われている。
天正6年(1578年)謙信急死後に起こった上杉家の後継者争い御館の乱が収束したあとの戦後処理が行われる天正8年(1580年)から、景勝への取次役など側近として、同年8月15日(9月23日)には景勝印判状の奏者を務める。
天正9年(1581年)に、景勝の側近である直江信綱と山崎秀仙が、毛利秀広に殺害される事件が起きる。兼続は景勝の命により、直江景綱の娘で信綱の妻であった船の婿養子(船にとっては再婚)となり、跡取りのない直江家を継いで越後与板城主となる。
上杉景勝は御館の乱に際して甲斐武田氏と同盟関係を結んでいた(甲越同盟)。天正10年(1582年)には織田信長による武田領への侵攻で甲斐武田氏は滅亡し、旧武田の領地には織田家臣が配置されたが、6月2日の本能寺の変で信長が横死するとその領地は無主状態となりその地を巡る天正壬午の乱が起こる。景勝は武田方に帰属していた北信国衆や武田遺臣を庇護し北信の武田遺領を接収し、兼続は信濃衆との取次を務めている。
天正12年(1584年)末から兼続は内政・外交の取次のほとんどを担うようになる。これは兼続死去まで続くことになった。当時の上杉家臣たちは景勝を「殿様」「上様」、兼続を「旦那」と敬称し、二頭政治に近いものであった。
新発田重家の乱において天正11年(1583年)、当時新潟は湿地帯だったために豪雨により上杉勢が敗北する。兼続はこの対策として、川筋が定まらない土地の対策として、信濃川に支流の中ノ口川を開削するなどし、現在の新潟平野の基礎を造り、着々と新発田勢を追い詰めていく。天正13年11月20日(1586年1月9日)、新潟城と沼垂城から新発田勢を駆逐した。これにより新潟湊の経済利権を失った新発田重家は急速に弱体化した。天正15年10月28日には新発田城を落城させ、乱は収束。
天正16年8月17日(1588年10月7日)には景勝に従って上京し須田満親・色部真長らと共に豊臣秀吉から豊臣の氏を授けられ、豊臣兼続として改めて山城守の口宣案を賜る。
天正17年(1589年)の佐渡征伐に景勝と共に従軍。その功により、平定後に佐渡の支配を命じられる。
豊臣政権時代
安定した豊臣政権の中で、兼続は戦乱で疲弊した越後を立て直そうと奔走する。兼続は農民に新しい田畑の開墾を奨励。越後の平野部は兼続の時代に新田開発が進み、現在に至る米所の礎となった。さらには産業を育成し、商業の発展に努めた。その元となったのが青苧(あおそ)と呼ばれる衣料用繊維で本座といい、魚沼郡に自生していたカラムシという植物から取れる青苧は、木綿が普及していなかった当時、衣服の材料として貴重なものであった。蒲生氏の支配時期においても青苧は特産品であったが。この青苧を増産させ、織り上げた布を京で売り捌き、莫大な利益を上げた。京都へ輸出することを献策したのは、西村久左衛門乗安という人物である。兼続の施策は越後に謙信の時代に劣らぬ繁栄をもたらした。
文禄4年(1595年)1月、景勝が秀吉より越後・佐渡の金・銀山支配を任せられると、兼続は立石喜兵衛、志駄義秀を金山奉行に命じる。
慶長3年(1598年)、秀吉の命令で景勝が越後から会津120万石に加増移封された際、兼続には出羽米沢に6万石(寄騎を含めると30万石)の所領が与えられている。またこの国替えで、上杉領は最上領によって会津・置賜地方と庄内地方に分断された。兼続は、この分断された領国の連絡路として、朝日軍道と呼ばれる連絡路を整備した。朝日連峰の尾根筋を縦走する険しい山道で、関ヶ原の合戦後はほぼ廃道となった。
関ケ原の前哨戦のきっかけ
慶長3年8月18日(1598年9月18日)に秀吉が死去すると、徳川家康が台頭するようになる。景勝・兼続主従は、前領主・蒲生家の居城若松城に代わり、新しく神指城の築城を始めており、これは戦のためではなく会津の町を新たに作り直す狙いがあったとされる。しかし、一方で兼続は本来国替えの引継ぎで半分残していかなければならない年貢を、景勝に無断で全て会津へ持ち出しており、年貢を持ち逃げされてしまった堀秀治が返還を求めても無視した結果、怒った秀治が上杉家謀反を家康に訴えると、家康は上杉家を詰問する。このとき家康を激怒させることになり、会津遠征を決意させるきっかけとなった返書直江状の文面は、偽物か後世に加筆された可能性もあり真偽は定かではない。ただ、家康の上杉征伐を諌止した豊臣奉行衆の書状には「今度、直江所行、相届かざる儀、ご立腹ご尤もに存じ候」「田舎者に御座候間、不調法故」などとあることから、家康を激怒させた兼続の書状が存在したことは事実のようである。奉行衆の諌止もあってか直江状のあとも上洛が計画されたが、讒言の真偽の究明が拒否されたため、景勝は上洛拒否を決断。関ヶ原の戦いの遠因となる会津征伐を引き起こした。
その後、石田三成挙兵のため、家康率いる東軍の主力は上杉攻めを中止。その後西軍側が敗戦となり、上杉軍は降伏ということになる。
江戸時代
慶長6年(1601年)7月、景勝とともに上洛して家康に謝罪する。家康から罪を赦された景勝は出羽米沢30万石へ減移封となり、上杉家の存続を許された。その後は徳川家に忠誠を誓う。
兼続は新たな土地の開墾を進めるために治水事業に力を入れた。米沢城下を流れる最上川上流には3キロメートルにわたって巨石が積まれ、川の氾濫を治めるために設けられたこの谷地川原堤防は「直江石堤(なおえせきてい)」と呼ばれている。また新田開発に努め、表高30万石に対して内高51万石と言われるまでに開発を進めた。また、町を整備し、殖産興業・鉱山の開発を推進するなど米沢藩の藩政の基礎を築いた。
上杉家と徳川家の融和を図るため、徳川家重臣本多正信の次男・政重を兼続の娘の婿養子にして交流を持ち、慶長14年(1609年)にはその正信の取り成しで3分の1にあたる10万石分の軍役が免除されるなど、上杉家に大きく貢献している。のちに政重との養子縁組が解消された後も本多家との交流は続いた。慶長19年(1614年)正月には松平忠輝の居城高田城築城の際、伊達政宗の指揮の下に、主君景勝とともに天下普請を行なった。同年の大坂の陣においても徳川方として参戦している。
元和5年(1619年)5月から9月にかけて景勝が徳川秀忠に従って上洛した際、景勝は兼続に命じ、将士に法令を頒布した。そして12月19日(1620年1月23日)、江戸鱗屋敷(現:東京都千代田区霞が関2-1-1警視庁)で病死した。享年60。
直江兼続という人物は、よくもわるくも、まっすぐな性格だったように思います。終生上杉景勝とともに政務をおこない上杉家のために行動しています。その行動を支えているのは上杉謙信の影響があるように思います。謙信が「義」を大切にする生き方と戦いの神「毘沙門天」を崇めていたことを見て育ち、影響されたと思います。そのまっすぐな生き方が、多くの方の信用を集める一方、野心のある人物からは煙たがられる、と私は考えます。

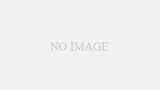

コメント