

その隣には方広寺があります。
このお寺にはあの「国家安康の鐘」があります。以前、書いた「以心崇伝」も関わりのある一件です。
天下を統一した秀吉が東大寺の大仏にならって大仏殿の建立をはじめたのですが、大地震による倒壊や火災による焼失というアクシデントが相次ぎ、慶長17年(1612)に息子の秀頼によってようやく完成しました。完成後、落慶供養を行う手筈となっていましたが、銘文の「国家安康」「君臣豊楽」が家康の名前を分断し、豊臣を君主とするものだと徳川家康から難癖がつけられました。これが大坂冬の陣の導火線となったといわれています。大仏殿及び大仏は1798年の落雷により大仏、大仏殿ともに焼失、天保年間に再建されましたが、こちらも火災にあってしまい大鐘が吊られた鐘楼、諸将の名が刻まれた石塁や石塔だけが往時の遺構です。
梵鐘は京都三条釜座鋳物師、名越(名護屋)三昌らによって1612年に製作されました。高さが4.2m、外径2.8m、厚さ0.27m、重さ82.7tと、とても大きい物で、奈良の東大寺・知恩院・方広寺と日本三釣鐘(重要文化財)に指定されています。草花や鳥獣と人の現世・来世を描いた天井絵も当時のままで残されています。(出展、方広寺 | 京都の観光スポット | 京都観光情報 KYOTOdesign (kyoto-design.jp))
「東海道中膝栗毛」の中にも方広寺の大仏は登場します。当時の有名な観光スポットだったのではないでしょうか。
徳川家康もそこまでしてまで、天下を取りたかったのでしょうか。周囲の人間の「家康に天下を取らせよう」という総意があったのではないかと、私は思います。「家康」なら戦乱のない時代が作れるという周囲の人間の思いが彼を動かしたとおもいます。そうでなければ、260年つづく戦乱のない時代は続かなかっただろうと私はかんがえています。

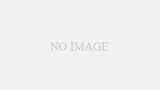

コメント